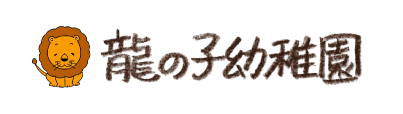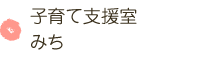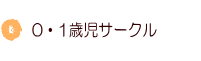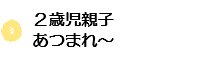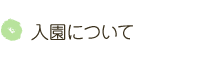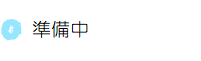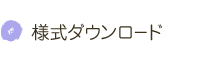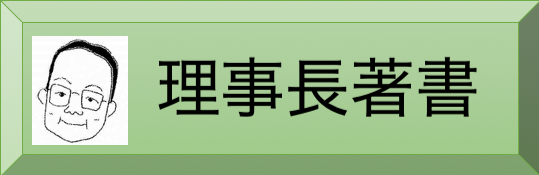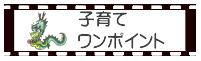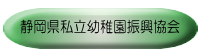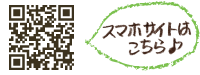早いもので令和3年もあと1ヵ月となりました。今年は緊急事態宣言が静岡県など多くの県に発出され、行動制限がされました。龍の子に於いても「家庭内保育のお願い」などにご協力いただき感謝申し上げます。コロナ禍でも開催された東京五輪・パラリンピックで日本選手の活躍に心躍らせました。現在は新型コロナウィルス感染が少し沈静化しています。このまま平穏な日常が取り戻せることを願っています。
10月28日㈭~30日㈯の3日間で「弁当の日」の上映会を行ないました。弁当の日とは香川県の小学校の校長をしていた竹下和男先生が、生徒に自分だけで作る弁当を持ってくる日を設定したことから始まっています。
調理をすることで『家族の有難さ』を知り、『計画や段取りを』を覚え、『工夫』することの大切さを知ります。また彩りを考える『感性』も磨かれます。そして自分の作った物を食べてもらおうという『周囲への配慮』、「ありがとう」と言ってもらい『幸せな気持ち』を感じることができます。でも一番は、調理をすることや調理準備をすることによって生まれる『親子の会話』です。これが親子関係の絆をより強いものにします。子ども達も親とのかかわりを通して調理の楽しさを知る機会にもなります。
本園でも月2回の「手づくり弁当の日」には1品だけでも自分でおかずを作ろう、それが無理な場合はお弁当箱に詰めるだけでもしようと提唱しています。
「弁当の日」を多くの学校で実践し、メディアでも取り上げられました。竹下先生自身も全国各地で講演会活動をされ大ブームとなったのですが、それがいつのまにか下火になってしまいました。このままではいけないと「弁当の日」という映画を作成し、上映会や講演会を全国各地で開催し、再び弁当の日を復活させたいとの想いから始まった「弁当の日」応援プロジェクトです。
「めんどくさいが幸せの近道」とのテーマで、小中学生や幼児、大学生に至るまで台所に立つ様子からその後の変化をドキュメンタリー風に構成されています。台所に立つことで子どもの「心」が変わっていくのが分かります。食事を作ることで、「家族に喜んでもらった経験」を得ることもできます。そのために誰かのために「自分の時間を割くこと」も苦にならなくなるのです。これが今後の人生に大きく作用すること感じます。以下は上映会に参加した保護者の感想です。
「弁当の日を通して幼児から大学生までの人たちの心の成長が見えました」「家族っていいな、大事だなとまず思いました」「食べ物を作る⇒生きる力をつける⇒心の成長につながる」「一品作ることで子ども自身の自信につながっていくことが分かった」「食が愛を伝え、『ありがとう』が溢れる、良いことばかりと思いました」「食べることは作った人の時間や手間をいただくことと再認識した」「時間がかかる、危ない、手間が増える…子どもを台所に立たせると思うことです。でも子供の顔は真剣、そして出来上がった時は達成感に満ちた顔をしています。共感し、勉強になる作品でした」。
そして何より助産師の話は衝撃的でした。「性につまずいた(望まない妊娠など)子の100%が家庭で食事を作ってもらっていない。食事をする機会や居場所がない。つまり愛情を受けていないと感じている」というものです。
最後に弁当の日の一期生が母親になって、2歳の我が子と台所に立っている姿は、ずっと引き継がれているんだと感激しました。
愛する人のために時間を割いて食事を作ることがどれほど大切なことなのかと再認識しました。
毎月あさがお(満3歳児)組の保護者に園長講話を行なっています。テーマを決めて「どうしてそれが大切なのか」とか「具体的にどのようにすれば良いか」を説いています。そして残りの時間を子育てQ&Aに充てています。今月は2回講話の機会があったので、1回をすべて子育ての質問時間にしました。今回の質問は「登園した後、別れる時に泣いてしまう」「事情があって母が1週間、家を空けるが今からの対処法は?」「うそをつくことがある」「兄弟ゲンカで手が出る」「寝る時は真っ暗が良いと聞いたが不安がる」「寝る前に絵本は何冊くらいが目安か?」「何でも自分でやりたがる。やり直すこともあるがそれで良いのか?」「何でもイヤイヤと言ってやらないが一時的なものなのか?」「スイミング練習中に爪を噛んでいる。対応策は?」以上が主な質問事項でした。まず子どもの心理状態を説明したうえで、具体的な対応策を示します。また過去に関わった子どもの事例などもできるだけ伝えるようにしています。
羚臣くんのお母さんがあゆみ(連絡帳)に丁寧に記してくれたので紹介します。
今日は園長講話の日でした。園長先生にいろいろな質問をし、アドバイスを頂きました。私はあゆみにも良く書きますが、「自分でやりたい」という羚臣の思い通りにならず怒ることについて相談しました。3歳前後は自立の心が芽生えて、何でも自分でやりたい時期、でも次の日にはやりたくなくて「ママやってー!!」と言ったりする…、園長先生は家の隅で羚臣のことをこっそり見ているのか(笑)と思うくらい的確でした。私の悩みどころを理解していてくださり、モヤモヤしていた心がスッキリしました。
「すべてを手伝うのではなく、『やってみる?』と聞いてみる」「まずはできやすいような言葉かけをしてキッカケを作ってあげる!!10あったとしたら、1.2.3は子どもにやるように促す、4.5.6はママが手伝ってあげる。7.8を再び子どもに声掛け、9.10はママが…、できない時はママからもあり…」というように自立の心を大切に育て、羚臣のやる気を少しずつ応援してあげたいと思いました。
どのお母さんの悩みも共通することがいっぱいありました。「うそをつく」という質問もありました。「うそだと分かっていても『ありがとう!』と言ってあげたり、『ママ知らなかったよ。ごめん!』と言ってあげましょう」と言う園長先生の言葉に、「え~!!その手があったのか!?」と笑ってしまいました。逆の発想で、うそをついている子どもに、うそを承知で信頼してあげる…、そうすると子どもの心は痛くなる(はず…笑)という考えはなかったです。このアドバイスはとても参考になります。息子も姉も「トイレに行ったよ!」とか「ごはん食べたよ!」とできてないのに言うことがあるので今度からは信じたフリをしてみます。
園長先生のお話でいろいろなエピソードも紹介されます。その中に自身のお父様のお話がありました。「子どもの頃に父に『泣くじゃない!!』と叱られた」だから「声をあげて泣いたことがない。大声を出して泣いている子を見ると羨ましいと感じた」。「声をあげて泣けることは自分の辛い気持ちを素直に表現しているのだからステキなこと」「それに対して、怒ったり、叱ったりしたら、子どもはどうして良いのか分からなくなってしまう」。とても共感できる内容でした。
子育て中の悩みは尽きませんが今日のアドバイスを参考にまた頑張ろうと思いました。
毎月15日は午前中がこども園井戸端会議(未就園児対象)、午後が子育て井戸端会議(在園児・卒園児対象)を行なっています。子育ての悩み、相談など、ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。