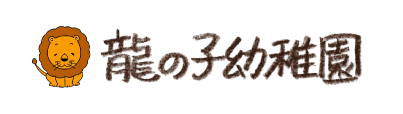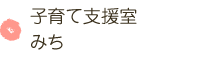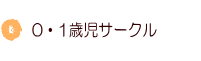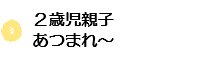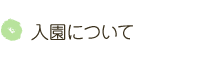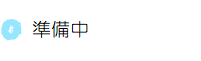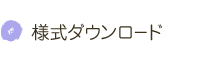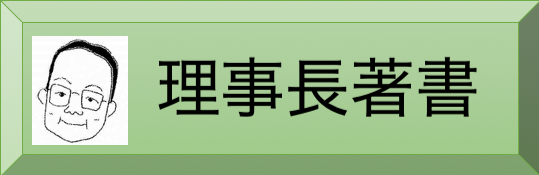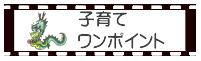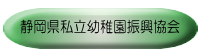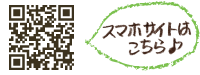2月に入り、暦の上では『大寒』も2日には終わり、3日には『立春』を迎えますね。立春は、春のはじまりを意味しています。先月、後半時期に差し掛かると、園庭の『北の野原(園庭北エリア)』には蝋梅が咲き、『西の泉(園舎西側アスファルトエリア)』の玄関手前では、河津桜が数個ですが花が咲くなど、春がもう直ぐそこまで来ているのかなと感じさせてくれました。穏やかで過ごしやすい日が続き、子ども達も朝から外で思い切り遊び込むことができ、園庭には元気な声と笑顔が溢れています。
この時期も園庭では、子ども達は花びら集めをしたり、土や石、小枝や落ち葉など自然と触れ合いながら遊ぶ姿があります。先日は、あさがお組(満3歳)の子ども達が農園で人参の収穫をしてきてくれました。自然の中で遊び生活することで、季節毎に実物に触れ、五感を重視した直接体験の中で育まれるさまざまな力が『生きる力』となっていくのだなと、子ども達の興味関心を持ってそれらと向き合っている時のイキイキとした姿から感じます。
現代の生活環境は、便利な生活様式やネット社会ということもあり、子ども達の身近な生活の中には間接体験が多くなっています。だからこそ、園生活という集団生活の場では、ちょっと不便なくらいの環境で、できるだけ自然と触れ合える環境で過ごすことが必要だと思います。自身で実際に触ったり、嗅いだり、味わったりする直接体験の中で、思考力・判断力・表現力が育まれていきます。大人が一つひとつの知識を教えるのではなく、好奇心をくすぐる環境を大切にし、子ども達自身がその中で主体的に活動し、探究していく姿を見守ってあげることが必要と考えます。自身で行った直接体験は、知恵となって生きる力となって、普段の生活に活かされていきます。子ども達の日々の体験が将来へと繋がっていくからこそ、転ばぬ先の杖で大人の価値観だけでストップをかけてしまわず、子ども達の直接体験のための自由な発想や行動を見守ってあげたいと思います。
本園では、月2回『手づくり弁当の日』があります。その日は、おにぎり又は、一品だけでも自分でおかずを作ろう、それが無理な場合はお弁当箱に詰めるだけでもしようと提唱しています。事前に、親子で献立を考え、買い物に一緒に行き、食材を選ぶこと、又、味見係をしてもらうことから始める家庭もあります。実際に自分で調理をすることで『家族の有難さ』を知り、『計画や段取りを』を覚え、『工夫』することの大切さを知ります。また彩りを考える『感性』も磨かれます。そして自分の作った物を食べてもらおうという『周囲への配慮』や、「ありがとう」と言ってもらい『幸せな気持ち』を感じることができます。でも一番は、調理をすることや調理準備をすることによって生まれる『親子の会話』です。このような関わりの中で『親子の絆』も育まれていきます。子ども達も親との関わりを通して調理の楽しさを知る機会にもなります。
今月、れんげ組(年中)の子ども達が『手作り弁当の日』に『お弁当作り』に挑戦します。実際に子ども達が買い物に行き(どっさり市を予定)、仲間と協力し合って食材を選び購入し、園にて調理をします。子ども達が、いつも楽しみにしている『手作り弁当』を子ども達自身で作り上げます。どんなお弁当ができあがるかな?その活動を通して、子ども達がどんな成長を見せてくれるのかワクワクします。どんなことがあっても、全ての経験がこれから先の生活に繋がっていきます。やりきった後の子ども達のキラキラした表情を想像すると、今からとても楽しみです。
14日(金)は、龍の子学園 龍の子幼稚園の創立44周年の記念講演会を行います。創立記念日は無認可の龍の子を立ち上げから署名運動を経て、今の龍の子があることを職員や保護者の皆さまにも知っていただくために毎年行っています。そして、皆さまに感謝の気持ちを込めて記念講演では子育てについての教育講演会をさせていただいています。会場はアミューズ豊田『ゆやホール』をお借りして、ご専門が小児栄養の名古屋短期大学保育科教授 小川雄二先生(『ママごはん』の『食育の学校』のコラムでお馴染みの先生です)をお招きし、『五感イキイキ!楽しく食べる食育で子どもが伸びる』をテーマにお話してくださいます。『食』に関するさまざまなことは、子ども達の成長に欠かせない『生きる力』を育んでくれます。お知り合いの方にも是非お声がけください。