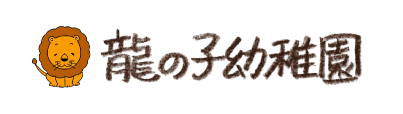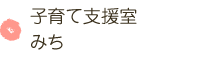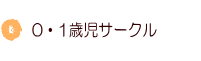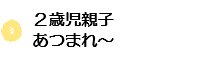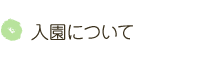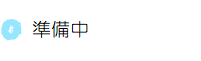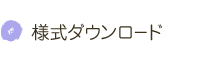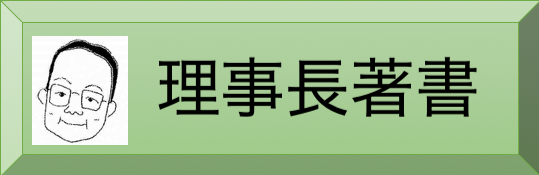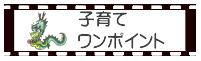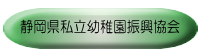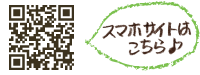秋分の日を迎え、やっと秋らしい心地よい風が吹くようになりましたね。今年は記録的猛暑続きの夏だったので、夏の疲れが少しずつ快復してきたところではないでしょうか。年々温暖化が加速する中で、今年も甚大な自然災害が起こり、特に北陸地方(石川県など)では少しずつ復興に向けて歩み出したところへ更なる災害が起きてしまいました。どうかこれ以上の災害が起こりませんようにと願わずにはいられません。ただ、この自然災害は、今はどこで起きてもおかしくないのです。他人事とは思わず、我が事に置き換えて、この先に繋がる今できる事を考えていく必要がありますね。
さてこの夏、終戦から79年を迎えました。改めて『戦争』そして『平和』について、親子で黙祷をしたり、一緒に絵本などを通して感じたり知るなどして、心を寄せたことと思います。風化させず、語り繋いでいくことが大切です。今も戦争をしている国があり、戦争は遠い過去の話ではなく、未だに私たちの近くにあります。昨年の夏、長野交流センターにて開催された『平和大会』(『緑十字機不時着を語り継ぐ会[緑語会]』主催)に参加をさせていただき、ちょうどその日は、太平洋戦争で日本がポツダム宣言を受諾した直後の1945年8月20日、軍使を乗せた『緑十字機』が磐田市内の鮫島海岸に不時着したまさにその同日でした。お話を伺う中で、大切に語り継ぎ伝承していこうと奮闘されていらっしゃる皆様の活動に感銘を受けました。長野地区にある園として、そこに通う子ども達に少しずつでもこの大切な歴史を語り継げたらと思いました。今年の8月20日・9月2日に全園児ではありませんが、『昔あったほんとうのおはなし』の紙芝居の絵をスライドで映し出し、読み聞かせを行いました。子ども達は「浜松」「磐田市」「鮫島」など知っている地名が出てきて、「磐田のお話?」「えっ?浜松って…知ってる!行ったことある!」「鮫島って、海の近くだよね⁈」「戦争のお話テレビでやってた!」「ね〜、これって本当のお話?」と何度も聞き返す子もいました。
紙芝居の大筋の内容]…今から79年前の8月20日の深夜、太平洋戦争終戦処理の文書などを運ぶ軍使らが乗る緑十字機が、沖縄県の伊江島から千葉県の木更津市に向かう途中で原因不明の燃料不足となり、同日深夜23時55分に磐田市の鮫島海岸に不時着。緑十字機に搭乗していたのは、進駐軍の日程や降伏要求文書を持ちフィリピンから帰国する任務を帯びていた河辺虎四郎・全権大使らだった。沖縄県の伊江村を経由して東京に向かう途中での不時着だった。磐田市の鮫島地区の住民の方々の助けにより、無事に東京に戻り任務を遂行した。
子ども達なりに何か感じることがあったようです。今後も読み聞かせをしていく中で、子ども達と共に改めて『平和』について考えていきたいと思います。紙芝居を通して、古き良き日本の知恵や助け合い、仲間を大切にし逞しく生き抜くパワーも感じとってくれたらと願っています。
夏やすみが明けて1ヵ月ちょっと経ち子ども達も生活リズムが戻り、遊びを通して友達との関わり合いも更に深めている姿が見られます。長期休み中は、お子さんにとっての友達第1号であるお家の方はもちろんですが、きょうだいや親戚・近所の子、園の友達などとたくさん遊んで、さまざまな経験をして成長したんだと思います。子ども同士で遊びが発展し関わり合いが深まり始めると、さっきまで楽しく遊んでいたはずなのに突然トラブルに発展することもありますね。子ども同士、時にはケンカをすることもあります。特に、幼児期は相手の立場に立って物事を考えることが難しいため、互いの考えや要求がぶつかったりした時に譲り合うなどの表現や言葉が咄嗟に出ず、意思疎通が上手くできず、叩いてしまったり、噛みついてしまうなどの身体的な攻撃行動が見られたりします。でも、子どもは発達と共にケンカの原因や方法は変化していきます。友達と仲良くすることはとても大切なことですが、心の発達においては、怪我や危険性のない範囲ではケンカを経験することはとても大切なことだとも言えます。子どもにとっては、ケンカを通じて自分の言い分を訴えるだけでなく、相手は自分と違う意見や思いを持っているということに気づく機会でもあります。その経験をもとに相手の気持ちを考え、自分の思いだけを主張するのではなく、感情をコントロールすることを少しずつ学んでいきます。また、ケンカをして少なからず気まずい思いもすることで、相手と仲良くした方が楽しいし、気持ちよく過ごせるということも、感じる機会になります。いろいろな相手との様々なやり取りを通して、自分の気持ちの伝え方やより良い対人関係を築いていくにはどうすればいいかを子ども自身が経験をしながら気づいていくのだと思います。
どんな時もまずは、お子さんの言い分、話したいこと…本当の気持ちを最後まで聞いてあげて欲しいのです。お子さんが話し始めたら大人の考えですぐさま否定してしまったり、相手について非難するなどはせず、まずは「うん、うん、そうか…」と、ただただ聞いてあげてください。お父さんやお母さんに話を聞いてもらえて、同意共感をしてもらえた安心感が持てると、自分の気持ちを理解してもらえたと思え、少しずつ落ち着いてきます。落ち着いたら、一緒に状況を整理してあげることで、相手の気持ちにも気づく心のゆとりを持つことができるので、相手はどんな気持ちだったか考えるよう促してみてください。相手の気持ちや立場を想像して考えたりしてみることで、共感性が育まれ思いやりの気持ちも育っていきます。また「どうすればいいかな?」「〇〇ちゃんだったらどうしたい?」などと問いかけ、自分で考えさせてあげることで、問題解決していく力も育っていきます。
なかなか実際にケンカが起きた時に「子どものその先の育ちに繋がる!」と思ったり、見守ったりは難しいかもしれませんが、身近な大人の関わりによって子どもの心の豊かさがずいぶんかわってくるので、少しでも子どもの成長に繋がる関わりをしてあげたいですね。
本園理事長著書『子育て99ハンドブック』の『第3章 お友達できるかな(P34~38)』をぜひご覧になって、お子さんとの関わりの参考にしていただけたらと思います。